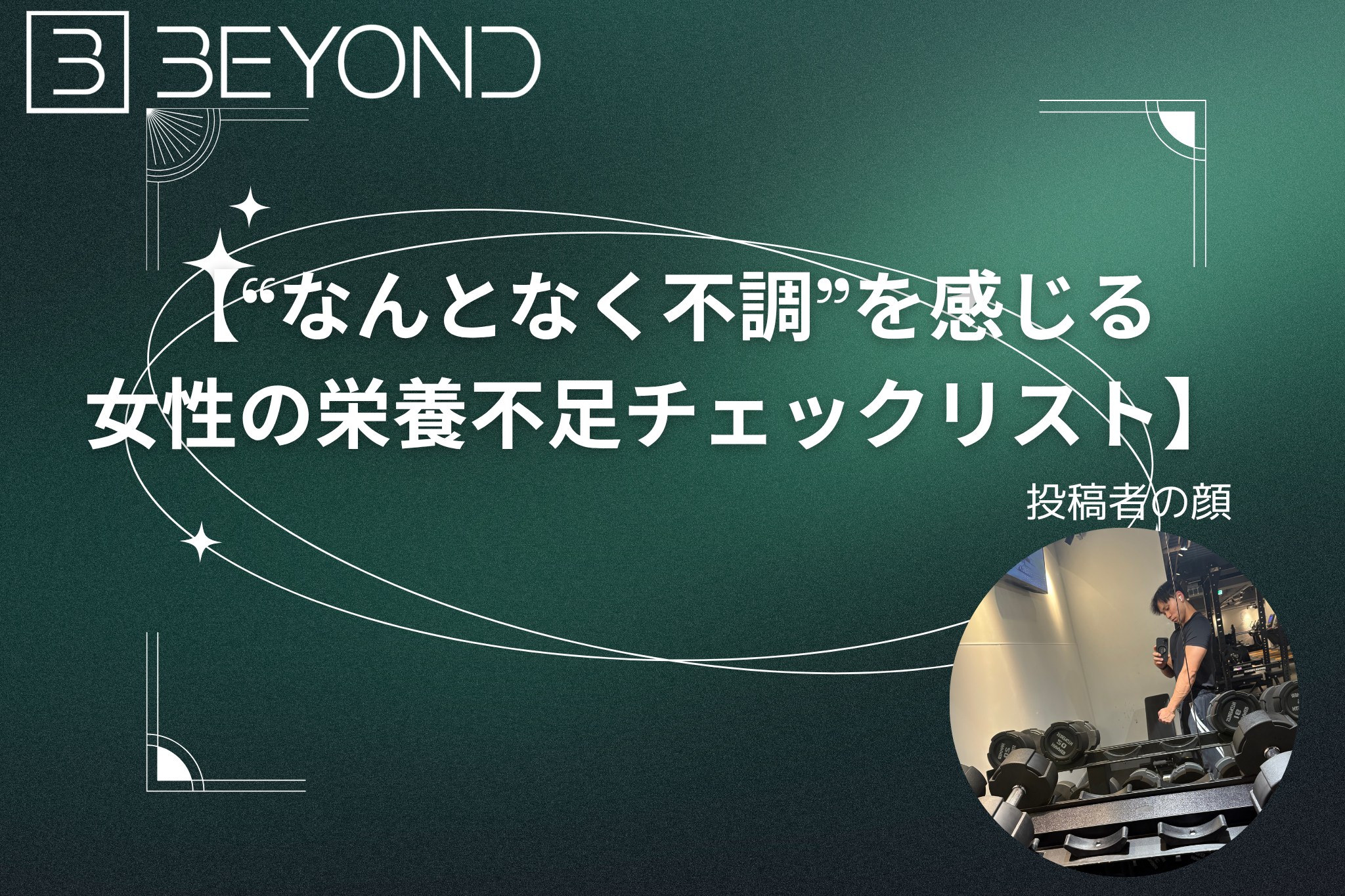筆者:BEYOND 四ツ谷麹町店 戸田 日陽
・役職 BEYOND 四ツ谷麹町店 トレーナー
・経歴 BEYOND trainer school卒業
・実績 毎月200名以上のトレーニングサポート(2024年9月〜現在)
疲れやすい、やる気が出ない、肌荒れが治らない、イライラしやすい、眠りが浅い。病院で検査をしても「異常なし」と言われるものの、体調がすっきりしない。このような「なんとなく不調」に悩まされている女性は決して少なくありません。厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、20-40代女性の約78%が何らかの体調不良を自覚しており、その多くが明確な診断名のつかない不定愁訴に分類されています。
実は、これらの「なんとなく不調」の背景には、潜在的な栄養不足が隠れていることが多くあります。現代女性の食生活は、カロリーは足りていても、必要な栄養素が不足している「隠れ栄養失調」の状態にあることが指摘されています。特に、ダイエット志向、外食・加工食品の多用、不規則な食事時間などにより、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸などの微量栄養素が慢性的に不足しています。
栄養不足による不調は、初期段階では検査値に現れにくく、「病気ではないが健康でもない」状態が続きます。しかし、適切な栄養素を補給することで、これらの症状の多くは改善可能であることが、多くの研究で実証されています。重要なのは、自分の症状がどの栄養素の不足と関連しているかを正確に把握し、科学的根拠に基づいた改善策を実践することです。
この記事をご覧いただいている方へ。
この記事をご覧いただいている皆さまは、健康面に気を使い、食生活や運動習慣の見直し、フィットネスジムに通われている。もしくは、入会等をご検討されている健康意識の高い方々ではないでしょうか?
実際に、厚生労働省が、健康づくりのための身体活動基準・指針を作成し、生活習慣病予防のための運動を推進しています。
また、日本政策金融公庫が発表した消費者動向調査(令和3年7月)では、運動面や食に関する志向で、“健康志向”の方が多く年々と増加しています。
より皆様が、健康的で充実した人生を歩めるよう、誠意を込めて記事を執筆いたしましたので、どうか最後までご覧ください。
<その他資料>
※スポーツ庁の資料(新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健康状態等に関する調査研究(令和2年度))では、コロナ終息後のパーソナルトレーニングジムの利用者数は急増中。
※経済産業省の『特定サービス産業動態統計速報』の結果でも、フィットネスジム並びに、パーソナルジム利用者は数多くいらっしゃいます。
【PR】BEYOND四ツ谷麹町店

BEYONDはダイエット初心者から美ボディコンテストに出場したプロまで幅広いレベルの方が通う、パーソナルジムです。
過度な食事制限やトレーニングなく、ライフスタイルに合わせて無理なく継続できます。
コースは大きく以下3つにわかれているため、目的に合ったトレーニングを選択可能です。
| 料金(税込) ※最小プランの場合 | 内容 | おすすめ | |
| ライフプランニングコース | 月々10,100円~ ※281,600円 | パーソナルトレーニング 食事管理 | 初心者の方向け |
| ライフプランニングコース(サプリ付き) | 月々10,600~ ※296,720円 | パーソナルトレーニング 食事管理 サプリメント | 目標がある方向け |
| 回数券コース | 月々4,300円~ ※96,800円 | パーソナルトレーニング ストレッチ | 継続したい方向け |
※月々の費用はBEYONDの指定の信販会社を利用した分割料金になります。
特に回数券コースの月々4,300円~は、業界内でも最安値級で良心的です。
BEYONDが気になる方は、まず無料体験トレーニングを活用してみてください。
\今なら入会金50,000円が無料/
栄養不足が引き起こす身体のサイン

身体は栄養不足を様々なサインで知らせています。これらのサインを正しく読み取ることで、必要な栄養素を特定できます。
疲労・エネルギー不足のサイン
慢性的な疲労感は、複数の栄養素不足が複合的に作用して生じます。鉄欠乏による酸素運搬能力の低下、ビタミンB群不足によるエネルギー代謝の低下、マグネシウム不足による筋肉機能の低下などが主要な原因です。
朝起きられない、午後の強い眠気は、血糖値調節に関わる栄養素の不足を示唆します。クロム、亜鉛、マグネシウムの不足により、インスリン感受性が低下し、血糖値の乱高下が生じます。また、セロトニン合成に必要なトリプトファンやビタミンB6の不足も関与します。
運動後の回復が遅い場合は、抗酸化物質やタンパク質の不足が考えられます。ビタミンC、ビタミンE、セレン、亜鉛などの抗酸化栄養素が不足すると、運動による酸化ストレスから回復できず、疲労が蓄積します。
参考論文:Vitamins and Minerals for Energy, Fatigue and Cognition: A Narrative Review of the Biochemical and Clinical Evidence
精神・神経系のサイン
イライラしやすい、情緒不安定は、神経伝達物質の合成に関わる栄養素の不足を示します。セロトニン合成にはトリプトファン、ビタミンB6、ナイアシンが必要で、これらが不足すると気分の安定性が損なわれます。
集中力の低下、物忘れは、脳機能に重要な栄養素の不足と関連します。オメガ3脂肪酸(DHA、EPA)、ビタミンB12、葉酸、コリンなどが不足すると、神経細胞の機能や記憶形成に支障をきたします。
不安感、うつ気分は、複数の栄養素不足が関与する複雑な症状です。ビタミンD、オメガ3脂肪酸、マグネシウム、ビタミンB群の不足が、神経系の機能低下を引き起こし、精神的な不調につながります。
参考論文:L-Tryptophan: Basic Metabolic Functions, Behavioral Research and Therapeutic Indications
美容・外見のサイン
肌荒れ、乾燥、くすみは、皮膚の健康に必要な栄養素の不足を反映します。ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、亜鉛、必須脂肪酸などが不足すると、皮膚のターンオーバーや保湿機能が低下します。
髪のパサつき、抜け毛は、毛髪の構成成分や成長に関わる栄養素の不足を示します。タンパク質、鉄、亜鉛、ビオチン、ビタミンDなどが不足すると、毛髪の質や成長サイクルに異常が生じます。
爪の変化(割れやすい、白い斑点)は、ミネラル不足の典型的なサインです。亜鉛、鉄、カルシウム、マグネシウムの不足により、爪の強度や成長に影響が現れます。
参考論文:The Roles of Vitamin C in Skin Health
女性に不足しがちな栄養素TOP10
現代女性の食生活分析から明らかになった、特に不足しがちな栄養素を優先度順に紹介します。
| 順位 | 栄養素 | 不足率 | 主な不調症状 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鉄 | 65% | 疲労、息切れ、冷え、集中力低下 |
| 2位 | ビタミンD | 58% | 骨の痛み、筋力低下、うつ気分 |
| 3位 | カルシウム | 52% | 骨密度低下、筋肉のけいれん |
| 4位 | マグネシウム | 48% | 筋肉痛、不眠、イライラ |
| 5位 | 亜鉛 | 45% | 味覚異常、肌荒れ、免疫力低下 |
| 6位 | ビタミンB群 | 42% | 疲労、口内炎、神経症状 |
| 7位 | オメガ3脂肪酸 | 38% | 乾燥肌、関節痛、記憶力低下 |
| 8位 | 食物繊維 | 35% | 便秘、血糖値不安定 |
| 9位 | ビタミンC | 32% | 免疫力低下、コラーゲン合成不良 |
| 10位 | 葉酸 | 28% | 貧血、神経管欠損リスク |
鉄不足:最も深刻な栄養欠乏
鉄不足の症状チェック
- 朝起きるのがつらい
- 階段を上ると息切れする
- 手足が常に冷たい
- 集中力が続かない
- 氷を食べたくなる
- 爪が薄く、スプーン状に反る
- 髪が抜けやすい
- 月経量が多い
改善のための食事戦略: ヘム鉄(肉類、魚類)と非ヘム鉄(緑黄色野菜、豆類)を組み合わせ、ビタミンCと一緒に摂取します。茶類やコーヒーは食事の1-2時間後に摂取し、鉄の吸収阻害を避けます。
ビタミンD不足:現代女性の隠れた問題
ビタミンD不足の症状チェック
- 骨や関節が痛む
- 筋力が低下している
- 風邪をひきやすい
- うつ気分になりやすい
- 疲労感が抜けない
- 日光に当たる時間が少ない
- 魚をあまり食べない
- 室内で過ごすことが多い
改善のための生活戦略: 1日15-30分の日光浴を心がけ、鮭、さんま、きのこ類などビタミンD豊富な食品を週3回以上摂取します。必要に応じてサプリメントの活用も検討します。
マグネシウム不足:ストレス社会の栄養問題
マグネシウム不足の症状チェック
- 筋肉がつりやすい
- まぶたがピクピクする
- 不眠や浅い眠り
- イライラしやすい
- 頭痛が頻繁にある
- 便秘がち
- チョコレートを欲する
- ストレスを感じやすい
改善のための食事戦略: ナッツ類、種子類、緑黄色野菜、全粒穀物を積極的に摂取します。加工食品を減らし、天然の食材からマグネシウムを補給することが重要です。
症状別栄養不足チェックリスト

具体的な症状から、不足している可能性の高い栄養素を特定できるチェックリストを提供します。
疲労・エネルギー不足系の症状
朝起きられない、日中の強い眠気
可能性の高い栄養不足:鉄、ビタミンB12、葉酸、マグネシウム、ビタミンD
チェックポイント
□ 肉類を週3回未満しか食べない
□ 緑黄色野菜が不足している
□ 日光に当たる時間が少ない
□ ストレスが多い
□ 月経量が多い
運動後の回復が遅い、筋肉痛が続く
可能性の高い栄養不足:タンパク質、ビタミンC、ビタミンE、マグネシウム、亜鉛
チェックポイント
□ タンパク質摂取量が体重1kgあたり1g未満
□ 果物や野菜の摂取が少ない
□ ナッツ類を食べない
□ 加工食品が多い
□ 水分摂取が不足している
精神・神経系の症状
イライラしやすい、情緒不安定
可能性の高い栄養不足:マグネシウム、ビタミンB6、トリプトファン、オメガ3脂肪酸
チェックポイント
□ 甘い物を頻繁に食べる
□ カフェインを多く摂取する
□ 魚を週2回未満しか食べない
□ 睡眠時間が6時間未満
□ ストレス解消法がない
集中力低下、物忘れが多い
可能性の高い栄養不足:オメガ3脂肪酸、ビタミンB12、葉酸、鉄、コリン
チェックポイント
□ 青魚を食べる頻度が少ない
□ 卵を週3個未満しか食べない
□ 緑黄色野菜が不足している
□ 朝食を抜くことが多い
□ 水分摂取が不足している
美容・外見系の症状
肌荒れ、乾燥、くすみ
可能性の高い栄養不足:ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、亜鉛、オメガ3脂肪酸
チェックポイント
□ 緑黄色野菜の摂取が少ない
□ 果物を毎日食べない
□ 良質な油を摂取していない
□ 加工食品が多い
□ 水分摂取が1.5L未満
髪のパサつき、抜け毛
可能性の高い栄養不足:タンパク質、鉄、亜鉛、ビオチン、ビタミンD
チェックポイント
□ 極端なダイエットをしている
□ タンパク質摂取が不足している
□ 月経量が多い
□ ストレスが多い
□ 日光に当たる時間が少ない
栄養不足度セルフチェック

以下の質問に「はい」「いいえ」で答え、自分の栄養不足リスクを評価してみましょう。
食生活チェック(20項目)
基本的な食事パターン
- 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 外食やコンビニ弁当が週5回以上
- 野菜を1日350g未満しか食べない
- 果物を週3回未満しか食べない
- 肉・魚・卵・豆製品を毎食摂取していない
特定栄養素の摂取状況
- 乳製品を1日1回未満しか摂取しない
- 魚を週2回未満しか食べない
- ナッツ類や種子類をほとんど食べない
- 全粒穀物(玄米、全粒粉パンなど)を食べない
- 海藻類を週1回未満しか食べない
食事の質と習慣
- 加工食品やインスタント食品を週5回以上食べる
- 甘い飲み物やお菓子を毎日食べる
- アルコールを週5回以上飲む
- 食事時間が不規則
- 早食いの傾向がある
生活習慣と環境要因
- 日光に当たる時間が1日30分未満
- 運動習慣がない
- 睡眠時間が6時間未満
- 慢性的なストレスを感じている
- 喫煙習慣がある
症状チェック(15項目)
身体的症状
- 疲れやすく、疲労が抜けない
- 風邪をひきやすい
- 肌荒れや乾燥が気になる
- 髪がパサつく、抜け毛が多い
- 爪が割れやすい、白い斑点がある
精神的症状
- イライラしやすい
- 集中力が続かない
- 物忘れが多い
- やる気が出ない
- 不安感を感じやすい
機能的症状
- 便秘がち
- 冷え性
- 筋肉がつりやすい
- 頭痛が頻繁にある
- 眠りが浅い、不眠
評価結果と対策レベル
低リスク(該当項目0-10個): 現在の食生活を維持し、定期的な見直しを行いましょう。バランスの良い食事を心がけ、季節の変化に応じて食材を調整します。
中リスク(該当項目11-20個): 食生活の改善が必要です。特に不足しがちな栄養素を意識的に摂取し、生活習慣の見直しを行います。必要に応じて栄養士への相談を検討します。
高リスク(該当項目21-35個): 積極的な栄養改善が急務です。医師や管理栄養士への相談を強く推奨し、サプリメントの活用も検討します。生活習慣全体の大幅な見直しが必要です。
栄養不足改善のための実践プログラム
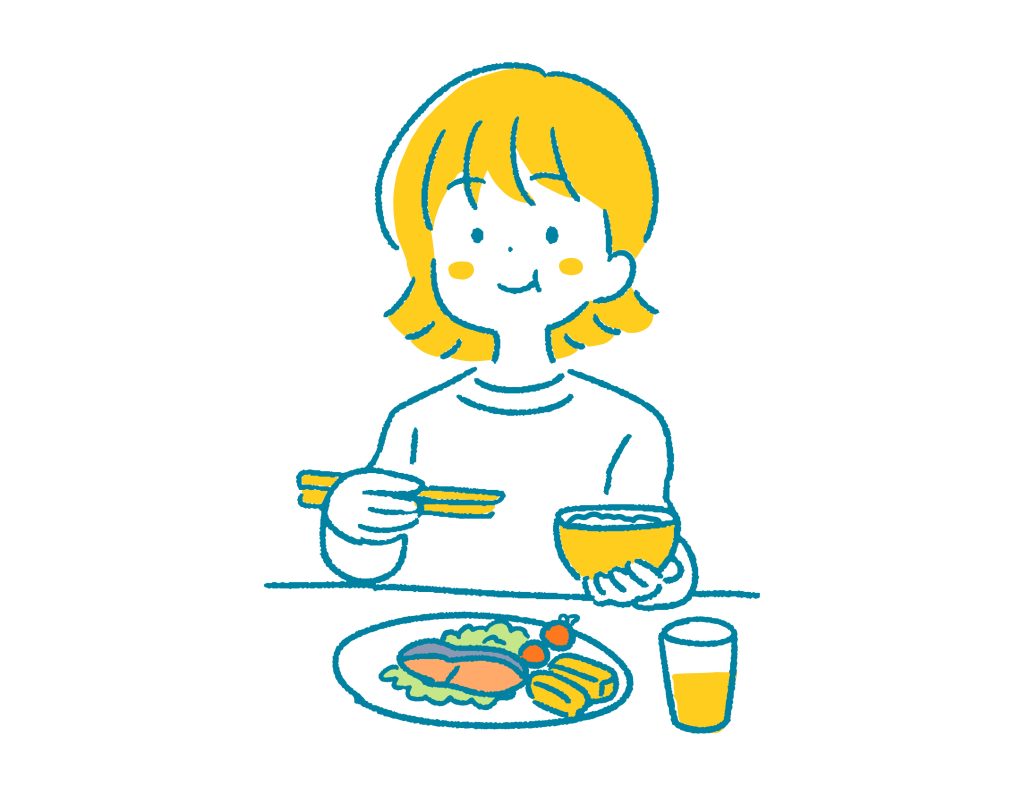
チェックリストの結果に基づいて、段階的に栄養状態を改善するプログラムを紹介します。
第1段階:基本的な食事パターンの確立(1-2週目)
優先改善項目
- 3食規則正しく食べる習慣の確立
- 毎食タンパク質源を1品目以上摂取
- 野菜を毎食1皿以上摂取
- 水分摂取量を1日1.5L以上に増加
- 加工食品の摂取頻度を半分に削減
具体的な行動計画
朝食には卵や納豆などのタンパク質と野菜を組み合わせたメニューを準備します。昼食は外食でも野菜の多いメニューを選択し、夕食は肉・魚・豆製品のいずれかを必ず含めます。間食は果物やナッツ類に変更し、甘い飲み物は控えます。
第2段階:重要栄養素の強化(3-4週目)
重点的に摂取する栄養素
- 鉄:レバー、赤身肉、あさり、ほうれん草
- ビタミンD:鮭、さんま、きのこ類、日光浴
- マグネシウム:ナッツ類、緑黄色野菜、全粒穀物
- オメガ3脂肪酸:青魚、亜麻仁油、くるみ
- ビタミンB群:豚肉、玄米、豆類、緑黄色野菜
週間メニュー例
月・水・金は魚料理(鮭、さんま、あじなど)をメインとし、火・木・土は肉料理(豚肉、牛肉、鶏肉)を中心とします。日曜日はレバー料理に挑戦し、毎日異なる色の野菜を5種類以上摂取します。間食にはナッツ類や季節の果物を選択します。
第3段階:個別症状への対応(5-8週目)
症状別カスタマイズ戦略
疲労感が強い場合は、鉄とビタミンB群を重点的に摂取し、造血機能を支援します。肌荒れが気になる場合は、ビタミンA、C、E、亜鉛を意識的に摂取し、抗酸化作用を高めます。精神的な不調がある場合は、オメガ3脂肪酸、マグネシウム、トリプトファンを含む食品を積極的に取り入れます。
効果測定と調整
週1回、症状の改善度を10段階で評価し、食事記録と照らし合わせて効果的な食材や組み合わせを特定します。改善が見られない症状については、摂取量の調整や新たな栄養素の追加を検討します。必要に応じて血液検査を実施し、客観的な改善度を確認します。
効果的なサプリメント活用法

食事だけでは改善が困難な場合、科学的根拠に基づいたサプリメント活用が有効です。
優先度の高いサプリメント
マルチビタミン・ミネラルは、基本的な栄養素を幅広くカバーし、食事の不足分を補完します。特に忙しい現代女性にとって、栄養バランスの保険として有効です。選択時は、鉄、ビタミンD、ビタミンB群、マグネシウムが適量配合されているものを選びます。
オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)は、魚の摂取頻度が少ない女性に特に重要です。1日1000-2000mgの摂取により、炎症の抑制、脳機能の改善、心血管系の健康維持が期待できます。酸化しにくい製品を選び、食事と一緒に摂取します。
ビタミンD3は、日照時間の少ない地域や室内勤務の女性に必須です。1日1000-2000IUの摂取により、骨の健康、免疫機能、精神的な安定性の向上が期待できます。脂溶性ビタミンのため、油分と一緒に摂取すると吸収率が向上します。
症状別特化サプリメント
鉄欠乏性貧血の場合は、ヘム鉄サプリメントが効果的です。非ヘム鉄よりも吸収率が高く、胃腸への負担も少ないため、継続しやすい特徴があります。ビタミンCと併用することで、さらに吸収率を向上させることができます。
ストレスや不眠に悩む場合は、マグネシウムサプリメントが有効です。グリシン酸マグネシウムやクエン酸マグネシウムは吸収率が高く、筋肉の緊張緩和や神経系の安定化に効果的です。就寝前の摂取により、睡眠の質改善も期待できます。
肌荒れや免疫力低下には、亜鉛サプリメントが推奨されます。1日15-30mgの摂取により、皮膚の修復促進、免疫機能の強化、味覚の正常化が期待できます。空腹時の摂取は胃腸障害を起こす可能性があるため、食後の摂取が安全です。
安全で効果的な摂取方法
適切な摂取タイミングにより、効果を最大化し、副作用を最小化します。脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は食事と一緒に、水溶性ビタミン(B群、C)は空腹時に摂取すると吸収率が向上します。ミネラル類は相互作用があるため、単独摂取または時間をずらして摂取します。
品質の確認により、安全性と効果を確保します。第三者機関による品質認証を受けた製品を選択し、添加物の少ないものを優先します。海外製品の場合は、日本の基準に適合しているかを確認し、信頼できる販売元から購入します。
医師との相談により、個人の健康状態に応じた適切な摂取を行います。既往症がある場合、薬物療法中の場合、妊娠・授乳中の場合は、必ず医師に相談してから摂取を開始します。定期的な血液検査により、栄養状態の改善度を客観的に評価します。
生活習慣改善で栄養吸収を最大化
栄養素を摂取するだけでなく、その吸収と利用を最適化する生活習慣の改善が重要です。
消化吸収機能の改善
胃酸分泌の最適化により、ミネラルの吸収を向上させます。食事前にレモン水や酢を摂取し、胃酸分泌を促進します。よく噛んで食べることで消化酵素の分泌も促進され、栄養素の分解と吸収が改善されます。
腸内環境の改善により、栄養素の吸収効率を高めます。発酵食品(ヨーグルト、味噌、納豆、キムチ)を毎日摂取し、善玉菌を増やします。食物繊維豊富な食品も併せて摂取し、腸内細菌のエサとなるプレバイオティクスを供給します。
食事のタイミングと組み合わせにより、栄養素の相互作用を活用します。鉄とビタミンCの組み合わせ、カルシウムとビタミンDの組み合わせなど、相乗効果のある栄養素を同時摂取します。逆に、阻害し合う栄養素は摂取時間をずらします。
ストレス管理と睡眠の質向上
慢性ストレスの軽減により、栄養素の消耗を防ぎます。ストレスホルモンのコルチゾールは、ビタミンC、マグネシウム、ビタミンB群を大量に消費するため、ストレス管理は栄養状態の維持に不可欠です。瞑想、ヨガ、深呼吸などのリラクゼーション技法を日常に取り入れます。
質の高い睡眠により、成長ホルモンの分泌を促進し、栄養素の利用効率を高めます。7-8時間の睡眠を確保し、就寝前のブルーライト暴露を避けます。マグネシウムやトリプトファンを含む食品を夕食に取り入れ、自然な眠りを促進します。
規則正しい生活リズムにより、体内時計を整え、消化機能を最適化します。毎日同じ時間に食事を摂り、体内の消化酵素分泌リズムを安定させます。朝の日光浴により、セロトニンとメラトニンの分泌リズムも調整します。
適度な運動の取り入れ
有酸素運動により、血流を改善し、栄養素の全身への運搬を促進します。週3回、30分程度のウォーキングや軽いジョギングにより、心血管系の機能が向上し、細胞レベルでの栄養素利用が改善されます。
筋力トレーニングにより、筋肉量を維持し、基礎代謝を向上させます。筋肉は栄養素の主要な消費者であり、筋肉量の維持により栄養素の利用効率が高まります。週2回程度の軽い筋力トレーニングで十分な効果が得られます。
柔軟性運動により、血流とリンパ流を改善し、老廃物の排出を促進します。ヨガやストレッチにより、筋肉の緊張を緩和し、栄養素の細胞への取り込みを改善します。深呼吸と組み合わせることで、リラクゼーション効果も得られます。
まとめ:なんとなく不調からの脱却
「なんとなく不調」の多くは、潜在的な栄養不足が原因となっています。重要なのは、自分の症状を正確に把握し、科学的根拠に基づいた栄養改善を継続的に実践することです。
チェックリストを活用して自分の栄養状態を客観視し、不足している栄養素を特定することから始めましょう。食事改善を基本とし、必要に応じてサプリメントを活用することで、効率的な栄養補給が可能になります。また、栄養素の吸収と利用を最大化するために、生活習慣全体の見直しも重要です。
今日から、毎日の食事に1つずつ栄養価の高い食材を追加してみませんか。小さな変化の積み重ねが、数ヶ月後の大きな体調改善につながります。適切な栄養管理は、単なる不調の改善だけでなく、エネルギーレベルの向上、美容効果、免疫力の強化、精神的な安定など、多面的な健康効果をもたらし、あなたの人生をより充実したものにする力を持っています。科学的根拠に基づいた栄養改善で、「なんとなく不調」から脱却し、本来の健康で活力に満ちた毎日を取り戻しましょう。
「なかなか一人で実践しづらい」
「何から始めたらいいか分からない」
という方も多くいらっしゃるかと思います。
実際に、当店のお客様でも同じような悩みを話してくれるお客様も多くいらっしゃいます。
そんな方々に対しても、食事指導と筋トレを通して「なんとなく不調」から脱却するお手伝いをさせていただいております。
是非とも、一人では実践しづらいという方は、無料体験トレーニングも行っているので気軽にお問い合わせしていただけると幸いです!